004インデックス投信・ETF: 2008年9月アーカイブ
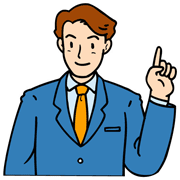 インデックス投信(インデックスファンド)とは、『日経平均(日経225)、TOPIX(東証株価指数)、MSCIコクサイ指数など市場の株価指数に連動した運用成績を目指す投資信託(ファンド)』のことです。
インデックス投信(インデックスファンド)とは、『日経平均(日経225)、TOPIX(東証株価指数)、MSCIコクサイ指数など市場の株価指数に連動した運用成績を目指す投資信託(ファンド)』のことです。例えば日経平均株価に連動するインデックス投信、ETF(株価指数連動型上場投資信託)であれば、日経平均株価にほぼ連動した運用成績を上げてくれるのです。
つまりインデックス投信に投資するという事は、株式や債券など金融の知識が特にない方でも、深く考えずに淡々と投資する事によって、日経225(日経平均株価)、TOPIX(東証株価指数)などの市場とほぼ同様の運用成績を上げる事ができるのです。

残念ながら素人が個別に選んで株式を購入した場合、日経平均株価などの市場を上回る運用成績を上げる事は難しく、かなりの確率で損することとなりますので、その点からしてみてもインデックスファンド、ETFは資産運用、投資信託初心者にはオススメかもしれません。
もちろん市場に連動するからといっても、必ず市場が上昇するわけではなく下降する場合もありますので短期間では浮き沈みがあるかもしれませんが、過去のデータから長期的に見れば市場は上昇する可能性が高いので、インデックス投信は短期的な運用ではなく、基本的に長期間運用する事によって効率的な資産運用が可能となるのです!
| 主な市場 | |
|
|
|
★日経225(日経平均株価)
日経225(日経平均株価)とは、東証一部上場の約1700銘柄のうち、225銘柄を対象として日本経済新聞社が算出、公表している株価指数のことです。
日経平均に連動するインデックスファンド、ETFの場合、約200銘柄に投資することによって、日経平均株価にほぼ連動した運用成績を上げてくれるのです。
★TOPIX(東証株価指数)
TOPIX(東証株価指数)とは、東証一部上場の全銘柄を対象として、東京証券取引所が算出、公表している株価指数のことです。
TOPIX連動型インデックス投信、ETFの場合、約1700銘柄に投資することによってTOPIX(東証株価指数)にほぼ連動した運用成績を上げてくれますので、TOPIX連動型インデックス投信、ETFは日経225連動型インデックス投信に比べて銘柄数が多いのため(約1700対200)、日経225連動型インデックス投信よりも分散効果が高く、より市場のベンチマークに沿った値動きが期待できるとされています。
★MSCIコクサイ指数
MSCIコクサイ指数とは、日本を除く世界主要先進国22ヶ国を対象として「モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル」が算出、公表している株価指数のことです。
| 個別株vs銀行預金vsインデックス投信 | |
|
|
|
 個別株というものは企業の業績次第で上がるかもしれませんし、下がるかもしれません。
個別株というものは企業の業績次第で上がるかもしれませんし、下がるかもしれません。このような不確定要素が多い個別株に、金融素人が投資するという事はパチンコなどと同様、一種のギャンブルに近いものがあります。
確かに個別株に的を絞って投資するほうが大きなリターンが得られるのも事実ですし、短期的に見れば素人でも個別株に投資して儲ける事は可能かもしれませんが、プロでも個別株で勝ち続けることは難しいとされていますので、素人ならなおさらのこと、素人が個別株で勝ち続けることは難しく、中長期的に見れば個別株で勝ち続けることはもはや不可能に近いといっても過言ではないのです。
素人が個別株で勝ち続けることがいかに難しいかは分かった。では素人でも長期間資産を運用するとして、確実に資産を殖やす方法はないのでしょうか?
まず思い浮かぶのは銀行預金です。
銀行預金、定期預金であれば確実に資産を殖やす事が可能かもしれませんが、正直言ってこの超低金利時代、資産が殖えると言っても良いかは微妙ですσ(^_^;)
そこで多少リスクがあるものの、銀行預金、定期預金に比べて遥かに大きく殖やす事ができる可能性があるのが投資信託で、投資信託の中でもリスクをコントロールし、安定したリターンが望めるのがインデックス投信、ETFなのです。
| インデックス投信の組み入れ株式 | |
|
|
|
インデックスファンドは市場に連動した運用成績を上げる事ができますが、では具体的にどのような企業の株式が組み入れられているのでしょうか?
これは日本、海外共に代表する企業の株式が組み入れられています。例えば・・・
日経225に連動するインデックスファンドに組み入れられている主な銘柄(2017年8月現在)
・みずほファイナンシャルグループ
・東京電力
・日本板硝子
・神戸製鋼所
・野村ホールディングス
・富士通
・ヤフー
・日立製作所
・東京ガス
・ファーストリテイリング
・ファナック
・ソフトバンク
・京セラ
・KDDI
 ・キヤノン
・キヤノン・信越化学工業
・東京エレクトロン
・セコム
・武田薬品工業
・TDK
・エーザイ
・アステラス製薬
・トヨタ自動車
・テルモ
・セブン&アイ・HLDGS
・デンソー
・電通
・NTTデータ
・味の素
・ANAホールディングス
・ブリヂストン
・本田技研工業
・日産
・ソニー
・三井物産
・パナソニック
MSCIコクサイ指数に連動するインデックスファンドに組み入れられている主な銘柄(2017年8月現在)
・アップル
・エクソンモービル
 ・ゼネラルエレクトリック
・ゼネラルエレクトリック・ジェブロン
・IBM
・マイクロソフト
・AT&T
・ネスレ
・プロクター&ギャンブル
インデックス投資であれば、低コストで上記のような世界を代表する企業へ分散投資することができるのです!
| インデックス投信を始める前に | |
|
|
|
インデックスファンドなどの投資信託を始めようと思い雑誌や書籍を読んでいるとさまざまな難しい言葉、分からない単語が出てくると思いますが、その中でも以下の2つの用語の意味は理解しておきましょう。
○騰落率(とうらくりつ)
騰落率(とうらくりつ)とは、過去のそのファンド(投資信託の基準価格など)の運用成績の事で、どれほど基準価格が上がったのか?下がったのか?を%で表示されます。
例えば、10,000円の基準価額の投資信託が12,000円まで値上がりした場合、その投資信託の騰落率は+20%になります(分配金は再投資することとして計算されます)。
ただ騰落率はあくまでも過去の運用成績の数字ですので、騰落率が高い金融商品だからといってその商品がこれからもリターン(騰落率)が高くなるとは限りませんので注意が必要です(騰落率は特にリターンと呼ばれる事もあります)。
○ポートフォリオ
ポートフォリオとは保有している資産の種類の内訳のことで、例えば100万円の資産がある方が、「預貯金20万円・株式50万円・債券30万円」の資産を持っていた場合は、「預貯金20%・株式50%・債券30%」のポートフォリオを組んでいるということです。

ではどのようなポートフォリオが理想なのでしょうか?
こればかりはプロでも意見が分かれますし、投資家の生活状況などによっても異なるので一概には言えませんが、基本的には国内株式だけなど、1つの市場、金融商品だけのポートフォリオを組むことはリスクをコントロールすることが難しいため望ましくありません。
具体的には、異なる値動きをする市場、金融商品へ分散投資し、ポートフォリオを組めばリスクをある程度コントロールすることが可能といわれていますので、『国内株式・海外株式・国内債券・海外債券』の異なる値動きをする4つの金融商品へ分散投資し、ポートフォリオを組む事が理想かもしれません。
ではこれら4つの金融商品をどのような割合でポートフォリオを組めば良いのでしょうか?
ただこれはプロでもどの市場が上がるのか?どの為替が上がるのか?を予想する事は難しいため、将来のことは分からないことを前提に資産運用することが大切ですので、単純に4分割(25%ずつ)したポートフォリオを組むことが基本となります。
| 関連記事 | |
|
|
|
⇒インデックス投信で世界へ分散投資!
⇒インデックス投信の手数料
⇒インデックス投信の税金
⇒インデックス投信 vs 銀行預金(定期預金)
⇒インデックス投信 vs ETF
⇒インデックス投信の始め方
⇒証券会社比較・オススメは?
⇒ドルコスト平均法
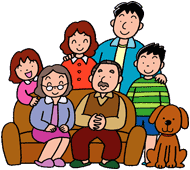
残念ながら日本は少子高齢化に歯止めがかからず、成長力が他の国に比べて期待できない?ですし、また日経平均株価など1つの市場にだけ投資する事は、一時的、または中長期的にその市場が低迷すれば運用成績が下がる可能性があるのでリスクが高くなりますので、日本の株、債券にだけ投資するのではなく、必ず世界の株、債券などにも投資し、分散投資する事がリスクをコントロールし、安定したリターンを得るためには重要になってきます。
つまり、リスクをコントロールしつつ、安定したリターンを得るためには値動きの異なる複数の市場に分散投資する事が何よりも重要となるのです!
| インデックスファンドで世界へ分散投資! | |
|
|
|
 株式市場では上がる銘柄もあれば下がる銘柄もあり、またいくら魅力的な金融商品、市場でも運悪くその金融商品、市場が大幅に下がる可能性は十分考えられます。
株式市場では上がる銘柄もあれば下がる銘柄もあり、またいくら魅力的な金融商品、市場でも運悪くその金融商品、市場が大幅に下がる可能性は十分考えられます。実際問題、素人だけでなくいわゆる金融のプロと呼ばれる人達でも、将来に向かってどの金融商品、市場が上がるか?下がるか?を予想する事はかなり難しいとされていますので、それなら1つの金融商品、市場にこだわるのではなく、いくつかの金融商品、市場に分散投資すれば運悪く全ての金融商品、市場が1度に全て値下がりする可能性はかなり低いため、リスクをコントロールする事ができるのです。
また、「日本、いや世界は今よりも数年後、数十年後には確実に成長している!(と思いたい・・・)」はずなので、短期的には大幅に下がる事もあるかもしれませんが、長期的に見れば株式市場自体は確実に右肩上がりに上がる事が予想されます。
ということは、個別銘柄の株式などは企業の業績次第で上場廃止になる可能性もありますがσ(^_^;)、市場(日経平均・MSCIコクサイ指数など)は上がって行くことが予想されるのであれば、それなら、それらの市場の動きに連動した商品があれば絶対、儲かるんじゃない?と思いますよね?そのような商品こそ『インデックスファンド(インデックス投信)/ETF』なのです。
しかしいくら将来的には右肩上がりに上がる事が予想されていても、短期的に見れば市場全体が低迷する事も十分、考えられるため、日経平均(日経225)など1つの市場だけに投資する事はリスクが高くなりますので、値動きの異なる複数の市場に分散投資する事が非常に重要となります。

つまり、『個別株ではなく市場に連動したインデックス投信、ETFで、1つの市場だけでなく異なる値動きをする市場、金融商品へ分散投資することによって、リスクを抑え、比較的安定したリターンを得る事が可能となり、理論上、また統計上、確実にリターンを得る事ができるのです!』
インデックス投信で分散投資する資産運用は2年後、3年後に資産が2倍、3倍になるような資産運用ではなく、上記の通り短期的には市場は低迷する可能性もありますので、基本的にインデックスファンドは10年、20年、30年と、長期間、運用すればするほど効率的な運用が可能となり、大きなリターンが得られるようになっているため、1日でも早くインデックス投信、ETFで分散投資を始めたほうが有利となるのです。
| 具体的な分散投資先とその割合 | |
|
|
|
具体的には・・・
・日本株式
・日本債券
・海外株式
・海外債券
上記の4つの市場に分散投資する事で比較的安定したリターンが得られる事が統計的にも分かっています。
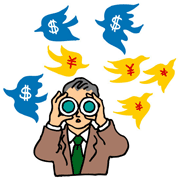
では4つの市場にどれほどの割合で投資すればよいのでしょうか?
こればかりは将来どの市場がより値上がりするのかは素人のみならず、プロでも予想する事が難しいと言われていますので、単純に4分割して投資すれば、金融についてそれほど詳しくない方でも特に何も考えずに資産運用することができます。
ちなみに統計的にはリターンの良かった市場はその後、低迷し、リターンの悪かった市場はその後、値上がりする可能性が高いので、例えば日本の株式が予想以上のリターンがあった場合、日本株式の資産を少し売却し、リターンが悪かった市場の投信を購入することによって、再び資産を4分割すればより安定したリターンを得る事が可能となります(資産のリバランス(調整))。
※ちなみに海外株式といっても『アメリカ・中国・インド・ブラジル』など、1つの市場に連動する株式ではなく、MSCIコクサイ指数(日本を除く22ヶ国の世界主要先進国を対象とした指数)などに連動した市場へ投資する事によってリスクをコントロールし、安定したリターンを目指します。
※日本債券へ投資する場合、インデックス投信だけでなく個人向け国債なども投資の対象になりますが、個人向け国債は中途解約の手数料が高いため、インデックスファンドの国内債権に投資するほうがベターです。
| インデックス投信でリスク管理 | |
|
|
|
 インデックス投信、ETFで分散投資すればリスクをある程度、管理する事が可能で、安定したリターンを得る事ができますが、それでもサブプライムローン問題、リーマン・ブラザーズ破綻、世界同時株安などによって年間マイナスになってしまうことがあるのも事実です。
インデックス投信、ETFで分散投資すればリスクをある程度、管理する事が可能で、安定したリターンを得る事ができますが、それでもサブプライムローン問題、リーマン・ブラザーズ破綻、世界同時株安などによって年間マイナスになってしまうことがあるのも事実です。しかしそのような場合でも『長期で資産運用していく場合はこのようなこともある』と割り切ることも大切ですよ。
ちなみにサブプライムローン問題、リーマン破綻、世界同時株安などがあっても、インデックスファンドなどで分散投資を心がけていれば、個別株に投資している投資家に比べ、被害(マイナス)は最小限に抑えられているというデータもあるようです。
| 関連記事 | |
|
|
|
⇒インデックス投信とは?
⇒インデックス投信の手数料
⇒インデックス投信(投資信託)の税金
⇒インデックス投信 vs 銀行預金(定期預金)
⇒インデックス投信 vs ETF
⇒インデックス投信の始め方
⇒証券会社比較・オススメは?
⇒ドルコスト平均法

インデックス投信(インデックスファンド)を購入し、保有したり、売却する場合には各種手数料がかかります。
具体的には『販売手数料・信託報酬・信託財産留保額』の3つの手数料が必要になります。
これらの各種手数料は目論見書に必ず記載されていますので購入前に必ず確認し、インデックス投信の場合は手数料の違いが勝負の分かれ道といっても過言ではありませんので、ファンド同士の手数料を比較し、少しでも手数料が安いファンドを購入し、運用していく事がもっとも大切となります。
特にインデックス投信はほぼ市場に連動した運用成績を上げられるため、同じ市場に連動するファンドであれば、どのファンドも運用成績はほぼ同じとなりますので、少しでも『販売手数料+信託手数料+信託財産留保額』が安いファンドを選ぶ事が基本となります。
※実際には上記3つの手数料以外にも『売買委託手数料・有価証券取引税・保管管理等』が必要で、これらの費用は目論見書には記載されておらず、運用報告書の費用の明細に記載されており、これらの数値は毎年変わります。
| 販売手数料 | |
|
|
|
 インデックスファンドなどの投資信託を購入する際に必要なのが『販売手数料』です。
インデックスファンドなどの投資信託を購入する際に必要なのが『販売手数料』です。この販売手数料は投資信託を販売する証券会社、銀行、郵便局が一定の範囲内で自由に設定する事ができるため、同じファンド(商品)であっても販売会社によって販売手数料が異なる場合がありますので注意が必要です。
例えば100万円のインデックス投信で販売手数料が0.5%の場合、「100万円-5千円(0.5%)=99万5千円」のインデックス投信を購入する事となります(販売手数料は購入時に差引かれます)。
もちろん同じファンドであれば販売手数料が安いほうが有利となり、基本的に大手証券会社、銀行、郵便局よりも、ネット証券会社、ネットバンクのほうが販売手数料が安い傾向にあります。
また最近では販売手数料が無料のインデックスファンドも増えてきており、販売手数料が無料のものを特に『ノーロードファンド』といい、特にインデックス投信は市場(日経平均など)に連動するため、同じ市場に連動するファンドであればほぼ同様の運用成績を上げられますので、販売手数料が無料のノーロードファンドのほうが有利となります(ノーロードだけで飛びつくのではなく、信託報酬なども比較しなければなりませんが)。

ただインデックス投信の場合、毎月、購入、積み立てていく事が多いと思いますので、そうなると毎月、販売手数料がかかると長期間、運用して行く場合には確実に不利となりますので、販売手数料はやはり安ければ安いほど、できればノーロードのものが選択肢の候補となりますね。
ちなみにETF(株価指数連動型上場投資信託)の場合、株式の売買と同様の販売手数料(購入手数料)がかかり、証券会社によって購入手数料が異なりますが、基本的に大手証券会社よりもネット証券会社(SBI証券・楽天証券など)のほうが安く購入できるようになっています。
※販売手数料が無料のノーロードファンドが増えてきていますが、販売会社は販売手数料を無料にしても下記の信託報酬を受け取る事ができるため、販売手数料無料=ノーロードの投資信託を販売する事ができるのです(下記の信託報酬は、「販売会社・投資信託会社・信託銀行」が受け取ります)。
| 信託報酬 | |
|
|
|
インデックスファンドなどの投資信託を保有している期間中、毎日必要になるのが『信託報酬』で、販売手数料はファンドを販売する証券会社、銀行、郵便局によって異なる事もありますが、この信託報酬はファンド(商品)によって決まっていますので、同じファンドであればどの販売会社で購入、運用しても同じとなっています。
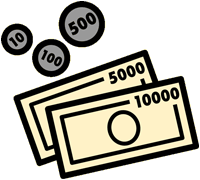
ただ信託報酬は日々、ファンドの純資産総額から一定割合で差引かれているため、投資家自身は信託報酬を支払っている意識が低いのですが、確実に差引かれていますので、当然、信託報酬が安いほうが有利となります。
またインデックス投信はアクティブ投信に比べてこの信託報酬が安くなっていますが、インデックスファンドよりもさらに信託報酬が安いのがETF(株価指数連動型上場投資信託)となっています。
※目論見書に記載されている信託報酬は年間にかかる数字ですので、毎日、目論見書に記載されている信託報酬が差引かれているわけではありませんσ(^_^;)
| 信託財産留保額 | |
|
|
|
購入した投資信託を中途解約する際に必要になるのが『信託財産留保額』で、一般的には中途解約時に差引かれるファンドが多いのですが、ファンドによっては購入時にすでに差引かれるものもあります。
また最近では信託財産留保額が無料のものもありますので、例えばインデックス投信で毎月、積み立てて、ある程度貯まったらETFへ移行する、リレー投資する際は、信託財産留保額が無料のファンドのほうが有利となりますね。
| 投資信託の手数料は高い? | |
|
|
|
 投資信託には上記のような手数料がかかりますが、当然プロが自分たちに代わって資産を運用してくれますので手数料がある程度かかる事は仕方ないと思いますし、逆にプロが代わって運用してくれると考えれば手数料はそれほど高くないと考える事もでき、手数料を払ってでも十分なリターンが期待できるのならば投資信託はかなり魅力的な金融商品なのです!
投資信託には上記のような手数料がかかりますが、当然プロが自分たちに代わって資産を運用してくれますので手数料がある程度かかる事は仕方ないと思いますし、逆にプロが代わって運用してくれると考えれば手数料はそれほど高くないと考える事もでき、手数料を払ってでも十分なリターンが期待できるのならば投資信託はかなり魅力的な金融商品なのです!また当サイトで推奨しているインデックス投信はアクティブ投信に比べてかなり手数料が抑えられているのですが、なぜインデックス投信は手数料が断然安いのでしょうか?
それは市場(日経平均など)に近づくような銘柄を単に選んでパッケージ化して販売しているだけなので、プロ(ファンドマネージャー)が意思決定に関わっていないため手数料を低く抑えることができるのです。
| 投資信託の具体的な手数料 | |
|
|
|
一口に投資信託といってもアクティブ投信、インデックス投信があり、さらに同じインデックス投信でもファンドによって各種手数料は異なりますが、平均すると投資信託の手数料は以下のような感じになります。
| 投資信託の手数料比較 | |||
| / | 販売手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
| アクティブ投信 | 0~3% | 0.5~2.5% | 0~0.3% |
| インデックス投信 | 0~2% | 0.4~0.9% | 0~0.3% |
| ETF(国内) | 株の売買と同じ | 0.1~0.3% | 株の売買と同じ |

上記の通り、インデックスファンドとアクティブファンドでは手数料にかなりの開きがあり、長期間、運用すればするほど手数料の違いが重くのしかかってきますので、長期間インデックス投信を上回る=市場指数を上回るアクティブ投信を見極める事ができない方は(そもそも長期間、市場指数を上回るアクティブ投信はごく僅かですが・・・)、インデックス投信に投資するほうが効率的な運用が出来るのです。
また大手証券会社、銀行、郵便局に比べて、ネット証券会社、ネットバンクのほうが販売手数料が安くなっていることが多いので、販売手数料を考慮すれば、残念ながら大手証券会社、銀行でインデックス投信を購入して運用していく時点でかなり不利になってしまうのです・・・( ´△`)
| インデックスファンドの純資産額 | |
|
|
|
投資信託、特にインデックス投信は同じ市場(日経平均など)に連動する銘柄(ファンド)であればほぼ同様のパフォーマンスが期待できるので、少しでも『販売手数料+信託報酬+信託財産留保額』が低い銘柄がオススメだと説明しましたが、手数料だけでなく『純資産額』にも注意したいところです。

純資産総額が少なくなりすぎるとファンドは効率的な運用、つまり分散投資が難しくなるために『繰上償還』が行われるのです。
繰上償還とは償還日が決まっていたり、無期限のファンドにもかかわらず、強制的に信託期間の途中で資産を償還(投資家に戻される事)されることです(⇒投資信託のリスク)。
純資産額は運用報告書で、繰上償還になる条件は目論見書に記載されており、具体的に繰上償還になる条件は以下のように記載されています。
「一部解約により受益権口数の合計が10億口を下回ることとなった場合、または受益者にとって有利になると判断される場合、またはやむを得ない事情が発生した場合等、投資信託約款に規定する信託の終了に関する条項に該当する事由が生じた場合には、途中で信託を終了させていただくことがあります。」
など・・・
繰上償還されてしまうと投資家は再び新たな投資先を探さなければならず不利となりますので、手数料が同じであれば純資産額の多いほうが繰上償還のリスクが少ないので当然オススメです(インデックスファンドを購入する場合、実際には手数料を重視しながらも、純資産額にも注意して投資する銘柄を選ぶようにしましょう)。
| 関連記事 | |
|
|
|
⇒インデックス投信とは?
⇒インデックス投信で世界へ分散投資!
⇒インデックス投信(投資信託)の税金
⇒インデックス投信 vs 銀行預金(定期預金)
⇒インデックス投信 vs ETF
⇒インデックス投信の始め方
⇒証券会社比較・オススメは?
⇒ドルコスト平均法
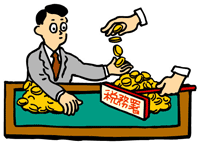
インデックスファンドなどの投資信託で利益をあげた場合、税金がかかりますので注意したいところです。
具体的には・・・『分配金・解約益・売却益・償還差益』、これら4つの場合に税金がかかります。
※投資信託を中途解約(売却・解約)した場合は税金だけでなく手数料(信託財産留保額)も必要となりますので注意しましょう(分配金には信託財産留保額は必要ありません)。
| 投資信託にかかる税金 | |
|
|
|
| 分配金(配当金) | 中途換金 | 償還差益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 特別 | 売却益 (買取請求) |
解約益 (解約請求) |
|||
| 公募株式 | 国内投資信託 | 配当所得 20.315% 源泉分離課税 申告分離課税 総合課税 3つの中から選択 |
非課税 | 譲渡所得 20.315% 申告分離課税 |
||
| 外国投資信託 | - | |||||
| 公募公社債 | 国内投資信託 | 利子所得 20.315% 源泉分離課税 申告分離課税 どちらか選択 |
- | |||
| 外国投資信託 | - | |||||
※税率は全て「所得税15%×復興特別所得税2.1%+住民税5%=20.315%」となっています(復興特別所得税2.1%は2037年まで)。
※上記の税率等は2017年8月現在の数値です。税制は頻繁に改正されていますので、証券会社のウェブサイトなどで必ずご自身でご確認ください。
◎源泉徴収

投資信託で出た利益から自動的に税金が差引かれるため基本的に確定申告の必要はありませんが、確定申告することも可能です(確定申告することによって配当控除が受けられる事があります)。
◎源泉分離課税
投資信託で出た利益を他の所得(給料所得など)とは別に計算し、税額を求め、自動的に税額が差引かれるため基本的に確定申告の必要はありません。
※差額徴収方式とは、外国での源泉徴収分との合計が20%になるように、国内の源泉徴収税額が調整される方式のことです。
◎申告分離課税
投資信託で出た利益を他の所得とは別に計算し、税額を求め、確定申告によって納税します。
| 投資信託の税金の扱い | |
|
|
|
投資信託の売却方法によって税金の扱いが以下の通り異なります。
・公募株式投資信託の分配金(配当金)⇒配当所得
・公募株式投資信託の売却益、解約益、償還差益⇒譲渡所得
・公募公社債投資信託の分配金(配当金)⇒利子所得
・公募公社債投資信託の売却益、解約益、償還差益⇒譲渡所得
買取請求?解約請求?などの売却方法については⇒分配金・解約・買取り
※売却益、解約益、償還差益(国内公募株式投資信託の解約や償還によって生じた損失)は譲渡所得なので損益通算できます。
| 関連記事 | |
|
|
|
⇒インデックス投信とは?
⇒インデックス投信で世界へ分散投資!
⇒インデックス投信の手数料
⇒インデックス投信 vs 銀行預金(定期預金)
⇒インデックス投信 vs ETF
⇒インデックス投信の始め方
⇒証券会社比較・オススメは?
⇒ドルコスト平均法

統計的に見るとインデックス投信(インデックスファンド)で分散投資した場合の利回りは『3~7%(10年以上運用した場合)』とされています。
ちなみに預け入れる金額、銀行によって大きく異なりますが銀行普通預金、定期預金の利回りは以下の通りとなっていますので、リスクを恐れず株や投資信託に投資した人のほうが遥かに大きなリターンを得る事ができるのです!
・銀行普通預金⇒『0.001~0.02%』
・銀行定期預金⇒『0.01~0.25%』
※上記は2017年8月現在の金利です。
この数字ではあまりイメージがわかないと思いますので具体的に計算してみましょう。
例えば1,000万円の資産を定期預金「利率0.25%」、インデックス投信「利率5%」で運用した場合(複利計算)、10年後にはどれほど差が出てくるのでしょうか?
※下記は税引き後の数値で、税率は「所得税15%×復興特別所得税2.1%+住民税5%=20.315%」で計算しています。
| 利率 | 利率 | 運用益 | 総資産 |
| 定期預金 1,000万円 |
0.25% | 252,827円 | 10,252,827円 |
| インデックス投信 1,000万円 |
5% | 6,288,942円 | 16,288,942円 |
どーです?10年間で約600万円も違ってくるのです!

では毎月5万円ずつ20年間(元本1,200万円)積み立てた場合、定期預金「利率0.25%」、インデックス投信「利率5%」で運用した場合(複利計算)、20年後にはどれほど差が出てくるのでしょうか?
| 利率 | 利率 | 運用益 | 総資産 |
| 定期預金 月5万円×20年 |
0.25% | 242,941円 | 12,242,921円 |
| インデックス投信 月5万円×20年 |
5% | 6,223,573円 | 18,223,573円 |
この条件でも20年間で約600万円以上も違ってくるのです!
以上のことから資産が少ないからこそ、少しでもリターンを得るために投資、資産運用を考えなければならないのではないでしょうか?
単利?複利?⇒単利と複利
もちろんインデックス投信には各種手数料がかかりますが、インデックスファンドはアクティブファンドに比べて圧倒的に手数料、コストが安く、これらの手数料を払ってでも銀行預金(定期預金)に比べて遥かに大きなリターンが得られる可能性が高いのです。
また上記は運用期間10、20年間で計算していますが、複利計算では長期間運用すればするほどその差は広がって行きますので、長期間、超低金利の銀行預金(定期預金)で資産を運用する事は、逆にリスクが高いと言えるかもしれませんね。
| 関連記事 | |
|
|
|
⇒アクティブ投信vsインデックス投信
⇒インデックス投信とは?
⇒インデックス投信で世界へ分散投資!
⇒インデックス投信の手数料
⇒インデックス投信(投資信託)の税金
⇒インデックス投信 vs ETF
⇒インデックス投信の始め方
⇒証券会社比較・オススメは?
⇒ドルコスト平均法
 『究極のインデックス投信、インデックス投信の進化系といわれているのが、ETF(株価指数連動型上場投資信託)です。』
『究極のインデックス投信、インデックス投信の進化系といわれているのが、ETF(株価指数連動型上場投資信託)です。』ETF(株価指数連動型上場投資信託)とは、証券取引所に上場され、株式と同様に市場で売買できる投資信託の事で、インデックスファンドと同じように市場(日経平均・TOPIXなど)に連動した値動きをしますが、インデックス投信と違い取引時間内ならリアルタイムに随時、売買できる事が大きな特徴です(インデックスファンドは通常1日1回)。
インデックス投信はアクティブ投信よりもコスト(手数料)が安く、比較的安定したリターンを得る事が可能なのですが、実はインデックスファンド同様に比較的安定したリターンを得る事ができ、さらに場合によってはインデックス投信よりもコスト(手数料)が安くなるのが『ETF(株価指数連動型上場投資信託)』なのです。
欧米など世界的に見れば日本で上場されているETFの数はまだまだ少ないのですが、2008年3月25日、「3年後(2011年)にETFの本数を100本と現在の3倍に増やします」と、東京証券取引所の斉藤惇社長が発表したことから、日本でもETFの売買が活発になりました(2017年現在、東京証券取引所のETF上場数は国内ETF163+外国ETF47=210となっています)。
また2010年から日銀が大量のETFを買い入れ、その買い入れ額は年々増加し、2017年現在、ETF買い入れ総額(日銀のETF保有残高)は10兆円を超えています(^^;)
| ETFvsインデックスファンド | |
|
|
|
 市場(日経平均など)に連動した値動きをする事からほぼ同様の運用成績が期待できる両者(インデックス投信とETF)ですが、ではインデックスファンドとETFではどちらがお得、有利なのでしょうか?
市場(日経平均など)に連動した値動きをする事からほぼ同様の運用成績が期待できる両者(インデックス投信とETF)ですが、ではインデックスファンドとETFではどちらがお得、有利なのでしょうか?これは取引の仕方によってコストが異なってきますので一概には言えませんが、毎月、取引するような場合(積立する場合など)は販売手数料が安いインデックス投信が、比較的まとまったお金を一度に購入し、取引回数が少ない場合はETFが有利となります。
具体的な特徴とコスト(手数料)は以下の通りです。
| / | ETF | インデックス投信 |
| 取扱会社 | 全国の証券会社(国内ETFの場合) | 証券会社、銀行、郵便局 |
| 取引時間 | 株と同様リアルタイムで可能 | 通常1日1回程度 |
| 売買単位 | 数万、数十万円単位~ | 1万~可能 |
| 分配金 | 再投資できない | 自動的に再投資できるものが多い |
| 信用取引 | 可 | 不可 |
※銀行、郵便局ではETFは販売しておらず、さらに証券会社でも海外ETFを取り扱っている証券会社はまだそれほど多くありません。
ではコスト(手数料)はどれほど違うのでしょうか?
100万円を購入、10年間保有した場合・・・
| 手数料比較(例) | 購入時 | 年間 | 10年間 |
| ETF(国内) | 販売手数料1千 | 信託報酬0.2% | 千+2万=2万1千 |
| インデックス投信 | 販売手数料0% | 信託報酬0.5% | 0万+5万=5万 |
※分かりやすくするため分配金を再投資しないとして計算しています(ETFはそもそも再投資できませんが)。また上記の手数料はあくまでも例で、最低水準の手数料(販売手数料)で比較していますが、インデックスファンド、ETFの銘柄、購入する販売会社によって手数料(販売手数料)は大きく異なりますので注意しましょう。
 上記の通り、ETFはインデックス投信に比べ購入時にかかる販売手数料は若干、高めですが(証券会社によってETFの購入手数料はかなり差があります)、信託報酬が割安になっていますので、結果、売買回数が少ない場合は当然、ETFが有利となります。
上記の通り、ETFはインデックス投信に比べ購入時にかかる販売手数料は若干、高めですが(証券会社によってETFの購入手数料はかなり差があります)、信託報酬が割安になっていますので、結果、売買回数が少ない場合は当然、ETFが有利となります。こう見るとインデックス投信のほうが不利なようにも見えますが、ETFは一度に数万、数十万円単位でしか売買できず、販売手数料もインデックスファンドに比べ高いので、毎月、こつこつ積み立てて行くような場合はインデックス投信のほうが有利と言えるでしょう。
実際にはインデックス投信、ETFだけにこだわるのではなく、インデックスファンドとETFを組み合わせて資産運用していくことが理想的かもしれません。
例えば毎月インデックス投信で積み立て、一定額以上(例えば100万円以上)貯まったらETFに移行すれば、ETFのデメリットである購入時にかかる販売手数料を抑えることが可能なので、より効率的な運用が可能となるのです(リレー投資)。
また日経225(日経平均株価)、TOPIX(東証株価指数)に連動したETFだけでなく、海外の株価指数に連動したETFも徐々にではありますが日本の証券会社から購入する事が出来るようになっていますので、インデックスファンド同様、ETFで世界に分散投資する事も可能となってきています(海外のETFは国内ETFに比べてコストは高くなります)。
※インデックスファンドからETFへのリレー投資は必然的にインデックスファンドの売却を行うため、売却益があった場合は税金がかかりますので注意しましょう(⇒インデックス投信の税金)。
※当然、TOPIX、日経平均の指数が上下すれば購入価格(最低投資金額)も上下します。例えば「TOPIX連動型上場投資信託」の場合、TOPIXが「1,600」の時であれば約16万円が最低投資金額ですが、2008年秋のように株価指数が大幅下落し、TOPIXが800になれば最低投資金額は約8万円に下がります。
| ETFのオススメ証券会社は? | |
|
|
|
 ETFはまだ証券会社によってはそれほど多く取り扱っていないこともありますが、『SBI証券・楽天証券』の2社が比較的、豊富なラインナップとなっており、購入手数料も安いので、ETFを購入する場合はこの2社が候補となりますね。
ETFはまだ証券会社によってはそれほど多く取り扱っていないこともありますが、『SBI証券・楽天証券』の2社が比較的、豊富なラインナップとなっており、購入手数料も安いので、ETFを購入する場合はこの2社が候補となりますね。ちなみに国内ETFの場合、流動性(市場での売買のしやすさ)が高く、日経平均株価に連動したETFよりも銘柄数が多く、分散効果が期待できる『TOPIXに連動したETF』のほうがオススメだとされています(約1700 vs 200)。
国内ETFであれば購入単位が低く、流動性が高い『TOPIX連動型上場投資信託』がオススメです。
| 海外上場ETFで世界へ分散投資 | |
|
|
|
日本で上場されているETFだけでなく、海外上場ETFを取り扱うようになった証券会社も近年は増えていますので、日本にいながら世界の市場に連動するETFに投資する事が可能となり、投資家にとっては選択肢が広がるだけでなく、世界のETFで分散投資する事も可能な時代となりました。
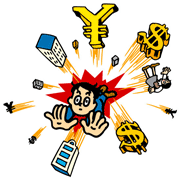
では海外のETFを購入する場合、どこの証券会社が良いのでしょうか?
やはり海外ETFも証券会社によって手数料にかなり差があり、ネット証券の『SBI証券・楽天証券』の2社が世界のETFを取り扱っている数も多く、手数料も安いのでオススメです。
※海外ETFは「国内手数料+現地手数料+為替手数料」が必要となりますので、国内ETFに比べて手数料が高くなります。
ちなみに海外ETFの場合、以下の銘柄が人気があるようです。
◎上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)
「中国・ブラジル・韓国・ロシア・台湾・南アフリカ・インド・メキシコ・UAE・エジプト・フィリピン・カタール・トルコ・マレーシア・インドネシア・タイ・コロンビア」など、世界23の新興国へ分散投資することができるETFで、新興国に期待する場合は是非ともポートフォリオに加えたいETFです(信託報酬0.25%)。
◎iシェアーズ MSCI EAFE
「英国・日本・フランス・ドイツ・スイス・オーストリア・スペイン・イタリア」など、北米(アメリカ・カナダ)以外の約20ヶ国の先進国株式に分散投資できるETFです(信託報酬0.34%)。
日本株が約20%組入れられていますので、TOPIX連動型上場投資信託をすでに保有しており、日本株を外したい場合は下記のiシェアーズ MSCI コクサイなどを保有するほうがベストです。
◎iシェアーズ MSCI コクサイ
「アメリカ(約60%)・英国・フランス・ドイツ・カナダ・スイス・オーストリア・スペイン・香港・スウェーデン」など、日本を除く約20ヶ国の先進国へ分散投資可能なETFです(信託報酬0.25%)。
◎バンガード・S&P500ETF
アメリカの株価指数S&P500に連動するETFです。
アメリカが含まれていない『iシェアーズ MSCI EAFE』などに投資する場合はポートフォリオに加えざるを得ないETFで、信託報酬が安いのも魅力です(信託報酬0.05%)。
ETFもインデックス投信同様、異なる地域へ分散投資することが非常に重要となりますので、日本株式のインデックスファンド、ETFを保有している場合は、日本が入っていない『iシェアーズ MSCI コクサイ』1つだけで日本を除く世界へ分散投資することも可能で、成長力に期待するのであれば世界25の新興国へ分散投資可能な『海外新興国株式(MSCIエマージング)』もポートフォリオに加えたいですね。
具体的には・・・
・『日本20%・アメリカ30%・新興国25%・先進国(アメリカ日本除く)25%』
・『新興国30%・先進国(アメリカを除き日本含む)35%・アメリカ35%』
など・・・
さらに具体的には・・・
・バンガード・S&P500ETF ⇒「35%」
・MSCIエマージング⇒「30%」
・iシェアーズ MSCI EAFE⇒「35%」
など・・・
 もちろん上記は株式のみのポートフォリオです。
もちろん上記は株式のみのポートフォリオです。株式だけに投資することはリスクをコントロールすることが難しくなりますので、リスクをコントロールし、安定したリターンを狙うためには当然、債券もポートフォリオに加えたいところです。
ただ債券ETFの数はまだ少ないので、ETFを積極的に利用したい場合でも、株式はETF中心で、債券はインデックス投信で運用せざるを得ませんが、当然、債券ETFのラインナップが充実し、選択肢が広がれば債権ETFもポートフォリオに加えたいですね。
※海外ETFをネット証券で購入する場合、外国株と同じ一般口座扱いとなりますので、売却益(損)があった場合は確定申告が必要となりますので注意しましょう。
| 関連記事 | |
|
|
|
⇒インデックス投信とは?
⇒インデックス投信で世界へ分散投資!
⇒インデックス投信の手数料
⇒インデックス投信の税金
⇒インデックス投信 vs 銀行預金(定期預金)
⇒インデックス投信の始め方
⇒証券会社比較・オススメは?
⇒ドルコスト平均法
 昔は投資信託は証券会社へ出向いて購入するしかありませんでしたが、1998年に銀行窓口で投資信託の販売が解禁され、いまでは証券会社の販売額を銀行での販売額が上回っており、さらにネットバンク、ネット証券の台頭によってパソコン、スマホがあり、ネットにさえ繋がればいつでも売買が可能となったため投資家にとっては株、投資信託、FXはより身近な金融商品となっています。
昔は投資信託は証券会社へ出向いて購入するしかありませんでしたが、1998年に銀行窓口で投資信託の販売が解禁され、いまでは証券会社の販売額を銀行での販売額が上回っており、さらにネットバンク、ネット証券の台頭によってパソコン、スマホがあり、ネットにさえ繋がればいつでも売買が可能となったため投資家にとっては株、投資信託、FXはより身近な金融商品となっています。ではこれから投資信託を始める場合、どこで購入すればよいのでしょうか?
まずインデックスファンドは市場(日経平均、TOPIXなど)に連動する投資信託ですので、同じ市場に連動するファンド(銘柄)であれば運用成績はほぼ同じになりますので、運用成績が同じであれば当然、手数料が安いインデックス投信を購入したほうが有利に決まっています。
しかし運用成績がほぼ一緒になるにもかかわらず、ファンド(銘柄)ごとに販売手数料が異なり、さらに同じファンド(銘柄)であっても投資信託を販売する証券会社、銀行によって販売手数料が異なる事があるので注意が必要です。
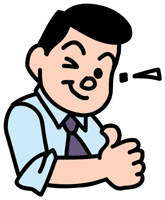
インデックス投信を購入、保有する場合、まずは購入するときにかかる『販売手数料』と、保有期間中にかかる『信託報酬』の手数料が必要となり、信託報酬はインデックスファンドの商品ごとにどこで購入しても一緒なのですが、販売手数料は各証券会社、銀行が一定の範囲内で自由に設定できるため、同じファンド(銘柄)でも証券会社、銀行によって販売手数料が異なる場合があるのです。
またいまでは販売手数料が無料の『ノーロード型インデックス投信』の数も増えてきましたので、インデックスファンドを始める場合、手数料(販売手数料)が安いファンド、証券会社で購入する事が基本中の基本となります。
| 扱っているインデックス投信の数 | |
|
|
|
インデックス投信は同じ商品であれば販売手数料が安い証券会社、銀行で購入するほうがお得なのは分かりましたが、いくら手数料が安くても扱っているインデックス投信の数が少なければ使い勝手はよくありません。
⇒証券会社比較を参考に、ノーロード型インデックス投信、ETF(国内だけでなく海外ETFも)を多く扱っている証券会社、銀行がオススメです。
| インデックス投信を始めよう! | |
|
|
|
上記の事を頭に入れて、インデックス投信を始める事となった場合、具体的には以下のような流れで始める事となります。
1:投資信託(インデックス投信)を始める決意をする!

いくら投資信託、インデックスファンドの知識を身に付けたからといって行動に移さなければ何も始まりませんので、まずはインデックス投信を始める決意をしましょう(たいした決意ではないと思いますが・・・)。
2:証券会社(銀行)の口座開設
投資信託(インデックス投信・ETF)を始めるには当然、投資信託(インデックス投信・ETF)を扱っている証券会社、銀行の口座を開設しなければ取引ができませんので、「⇒証券会社比較」を参考にして口座を開設しましょう!
3:月々の予算を決める
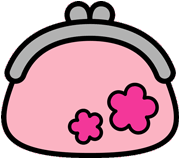
月々いくら投資信託(インデックスファンド・ETF)に投資する事ができるか、予算を決めましょう。
基本的にインデックス投信、ETFは長期運用する事になると思いますので、毎月無理なく続けられる金額を決め、『ドルコスト平均法』などを参考に毎月、購入(積立)していきましょう。
また将来的に何歳までにいくら投資信託(インデックス投信・ETF)で貯めたいのかを考えればおのずと月々いくら購入すれば良いのかがわかりますので、「⇒単利と複利」を参考に計算してみましょう。
基本的にインデックス投信の場合は、『国内株式・海外株式・国内債券・海外債券』の4つの市場に分散投資することによってリスクが低くなり、安定したリターンを得る事が可能となりますので、初めてインデックスファンドを始められる方は毎月、一定額を上記4つの市場に4分割して投資することをオススメします。
4:資産のリバランス(微調整)

インデックス投信で分散投資すれば、間違いなく1年後にはプラスになった市場とマイナスになった市場がでてき、ポートフォリオ(資産の内訳)のバランスが崩れますが、統計的に見てプラスだった市場はその後、低迷し、マイナスだった市場はプラスに転じる可能性が高いので、1~2年に1回は再度資産が4分割になるようにプラスだった市場の商品を売却し、マイナスだった市場の商品を購入する『資産のリバランス』をすることをオススメします(税金、手数料のことを考えれば比率が上がった市場の商品を売却しなくても比率が下がった市場へ追加投資して再度4分割になるようにすることのほうが良いかもしれません)。
またインデックス投信よりも信託報酬が安いETFも積極的に利用したいので、インデックスファンドで一定額が貯まったら、ETFへ移行するリレー投資を行えばより効率的な資産運用が可能となります。
⇒インデックス投信 vs ETF
5:インデックス投信以外にも投資
インデックスファンドで分散投資すればリスクが低く、比較的安定したリターンを得る事が可能ですが、インデックス投信だけでなく、アクティブ投信、REIT(不動産投資信託)などについても勉強し、常に金融市場の動向を掴んでおくことも必要ですよ。
投資信託(インデックス投信・ETF)を始めるには上記の通り意外と?簡単ですので、まずは始めの一歩を踏み出す事が大切です。
もちろん短期的にはマイナスとなることもありますが、「長い目で見れば一時的にマイナスになることもある」と、割り切ることも大切ですよ。
| 関連記事 | |
|
|
|
⇒インデックス投信とは?
⇒インデックス投信で世界へ分散投資!
⇒インデックス投信の手数料
⇒インデックス投信の税金
⇒インデックス投信 vs 銀行預金(定期預金)
⇒インデックス投信 vs ETF
⇒証券会社比較・オススメは?
⇒ドルコスト平均法
 インデックス投信は市場に連動する投資信託ですので、同じ市場(日経平均、TOPIXなど)に連動するタイプのファンド(商品)であれば運用成績はほぼ一緒になりますが、同じファンド(商品)でも購入する証券会社(銀行)によって手数料(販売手数料)に差があり、正直言って手数料(販売手数料)の違いが勝負の分かれ道と言っても過言ではありませんので、インデックスファンドの場合はとにかく安い手数料(販売手数料)の証券会社(銀行)で購入する事が基本中の基本です!
インデックス投信は市場に連動する投資信託ですので、同じ市場(日経平均、TOPIXなど)に連動するタイプのファンド(商品)であれば運用成績はほぼ一緒になりますが、同じファンド(商品)でも購入する証券会社(銀行)によって手数料(販売手数料)に差があり、正直言って手数料(販売手数料)の違いが勝負の分かれ道と言っても過言ではありませんので、インデックスファンドの場合はとにかく安い手数料(販売手数料)の証券会社(銀行)で購入する事が基本中の基本です!そこでここではインデックス投信、ETFを扱っている本数が多い証券会社(銀行)、手数料が安い証券会社(銀行)を紹介し、具体的にどのファンド(商品)がオススメなのかを説明していますので、インデックスファンド、ETFを始めようと思われている方は参考にしてください。
また当サイト管理人である僕は個人的にもインデックス投信の投信積立などの資産運用を行っており、現在保有、積立しているインデックスファンド、運用資産額、運用損益などを楽天経済圏住人DCHIの資産運用で2億円を目指すまでのブログで完全公開しているので興味のある方はのぞいてみてください!
※インデックス投信を購入する場合の販売手数料は同じファンド(商品)でも販売会社(証券会社・銀行・郵便局など)によって一定の範囲内で設定する事が出来るため異なる場合がありますが、保有期間中にかかる『信託報酬』はファンド(商品)によって決まっていますので、どこで購入しても同じとなります(⇒インデックス投信の手数料)。
| インデックス投信?アクティブ投信? | |
|
|
|
証券会社の口座を開設し、インデックス投信を購入しようと思っても、どの商品がインデックスファンドか分からないかもしれません。
具体的には以下のような商品がインデックス投信です。

・国内株式の場合:「インデックス、日経225、TOPIX(トピックス)などの名前が付いている。」
・目論見書のファンドの概要に、『日経平均、TOPIXに連動する(追随する)こと目指す』などと説明されている。
ちなみにアクティブ投信の場合は目論見書のファンドの概要に、『日経平均、TOPIXなどを上回ることを目指す』と説明されています。
また海外株式、債券なども同様に、ファンド名に『インデックス』と付いていればそのファンドはインデックスファンドだと思って間違いありません。
また名称でなくても、販売手数料が無料だったり、信託報酬が安いファンドもインデックス投信の可能性が高いと思ってよいでしょう。
| インデックスファンドはネット証券、ネットバンクが有利 | |
|
|
|
インデックス投信などの投資信託は証券会社、銀行窓口で購入する事ができ、窓口で購入する場合は相談に乗ってくれますが、残念ながら大口の顧客以外の場合、正直それほど親身になって資産運用について相談に乗ってくれないことが多く、それどころか証券会社(銀行)側の儲けの多い商品を中心に勧められる事もありますので注意が必要です。
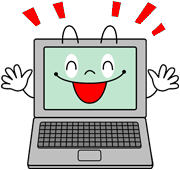
またそもそも最近はわざわざ証券会社(銀行)に出向かなくても、パソコン、スマホがありインターネットへ繋がる環境であれば投資信託の売買が可能となっている『ネット証券・ネットバンク』が増えており、実際問題、『大手銀行、大手証券会社よりもネット証券・ネットバンクでインデックス投信、ETFを購入したほうが販売手数料が安い事が圧倒的に多い』ので、わざわざ手数料の高い大手証券会社、銀行で購入するメリットは少ないため、ここでは『ネット証券・ネットバンク』を中心に紹介しています。
| 証券会社・銀行の比較 | |
|
|
|
※下記表の分散投資とは、『国内株式・海外株式・国内債券・海外債券』、4つ全てのインデックスファンドを扱っている場合は「◎」、1つでも扱っていない場合は「-」、ETFは国内上場ETFを扱っている場合は「○」、海外上場ETFも扱っている場合は「◎」としています。
| 証券会社(銀行) | 分散投資 | ETF | 特徴/手数料 |
| SBI証券 | ◎ | ◎ | 口座数、預かり資産共にNo.1のネット証券で、ノーロードファンド(販売手数料無料)の数は最も多く、販売手数料も格安だが、海外上場ETFの数は楽天証券に劣る。 |
| 楽天証券 | ◎ | ◎ | ノーロードファンドの数も多く、販売手数料も格安。特に海外上場ETFの数はTOPクラス。 |
| マネックス証券 | ◎ | ◎ | ネット証券大手だが国内債券ファンドを扱っていないのでマネックス証券だけでは効率的な分散投資ができないのがネック。 |
| 野村ネット&コール | ◎ | ◎ | 国内上場ETFの販売手数料が格安でノーロードファンドの数も豊富。 |
| カブドットコム証券 | ◎ | ○ | ノーロードファンドの数は豊富だが国内債券、海外ETFを取り扱っていないので・・・ |
| 楽天銀行 | ◎ | - | ETFは扱っていないがノーロードファンドの数が豊富で販売手数料も格安。 |
| ソニー銀行 | ◎ | - | ノーロードファンドを扱うようになり、ETFは扱っていないが、ソニーバンク証券の仲介でETFが購入可能。 |
※ETFは株式と同じ扱いですので国内上場ETFであればどの証券会社でも購入可能で、上記表を見れば分かりますが海外上場ETFはまだ購入できる証券会社が限られています。ちなみに銀行、投信販売専業会社ではETFは購入できません。
※上記は2022年1月現在の情報です。近年、各証券会社、銀行はインデックス投信、ETFに力を入れており扱うインデックスファンド、ETFの数も増えていますので必ずご自身でご確認のうえ口座を開設してください。
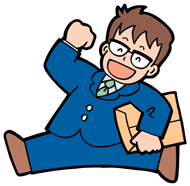
上記を見れば分かりますが、『楽天証券・SBI証券』の2社が、扱っているノーロードファンド(販売手数料無料)の数が多く、さらに海外上場ETFも取り扱っており、販売手数料も格安ですので間違いなくオススメです。
とりあえずこの2社のうちどちらかで口座を開設すれば、『国内株式・海外株式・国内債券・海外債券』への分散投資が可能で、販売手数料も格安なためコスト(販売手数料)面でも有利ですし、さらに国内、海外上場ETFを購入する事ができますので、インデックス投信からETFへのリレー投資も可能なため、複数の証券会社の口座を開設する必要はないため使い勝手も文句ありません。
| 各証券会社(銀行)のおすすめインデックス投信 | |
|
|
|
 一口にインデックスファンドといっても各証券会社、銀行によって扱っているファンド(銘柄)が異なりますので、口座を開設してもどの商品を購入すれば良いのかが分からないと思います。
一口にインデックスファンドといっても各証券会社、銀行によって扱っているファンド(銘柄)が異なりますので、口座を開設してもどの商品を購入すれば良いのかが分からないと思います。ただ下記の通り、実際はeMAXIS Slimシリーズかニッセイシリーズのインデックスファンドが手数料が最安なので、どの証券会社でインデックスファンドを買うにしても迷う必要はほとんどありません(特にeMAXIS Slimシリーズは他ファンドが手数料を下げれば同程度に下げてくる)。
※下記はあくまでも私がインデックス投信の分散投資を始める場合に購入する銘柄(ファンド)です。インデックスファンドを始める場合は必ず『目論見書・運用報告書』などをご自身でご確認のうえ購入するようにしましょう!(特に国内株式はインデックス投信でも各証券会社で複数の銘柄を扱っていますので、手数料だけでなく純資産額なども比較しましょう。)
| インデックス投信のおすすめファンド | ||||
| 投資先 | ファンド名 | 販売 手数料 |
信託 報酬 |
信託財産留保額 |
| 国内株式 | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0% | 0.154% | 0% |
| 海外株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | ||
| 米国株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | ||
| 国内債券 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132% | ||
| 海外債券 | eMAXIS Slim 先進国債権 | 0.154% | ||
※国内株式は日経平均⇒TOPIXでもOKです。
※販売手数料、信託報酬などは必ず確認し、ご自身の判断で購入してください。また証券会社(銀行)によっては積立には対応していない場合があり、その場合は面倒かもしれませんが毎月、自分で購入していくこととなります。『販売手数料・信託報酬・信託財産留保額』の説明は⇒インデックス投信の手数料
| 証券会社・銀行の比較 | |
|
|
|
 上記を見れば分かりますが、インデックス投信はノーロード(販売手数料無料)が主流となっていますので、どこで運用しても同じとなりますが、今後の資産運用の事を考えれば扱っている商品数が多い証券会社が便利です。
上記を見れば分かりますが、インデックス投信はノーロード(販売手数料無料)が主流となっていますので、どこで運用しても同じとなりますが、今後の資産運用の事を考えれば扱っている商品数が多い証券会社が便利です。これらを考慮すれば1つのみの口座開設にこだわるなら、『SBI証券・楽天証券』のいずれかで運用する事が最も手間がかからず、効率的な運用が可能だと思います。

色々考えるのが面倒な方は、「SBI証券・楽天証券」のいずれかで、全てにおいて手数料が最安レベルの『eMAXIS Slimシリーズorニッセイシリーズ』の4つで運用すればOK。
ちなみにインデックスファンドで分散投資していくには、ドルコスト平均法などによって毎月、一定額を購入、または積み立てていくと思いますが、証券会社(銀行)、またはファンド(銘柄)によっては自動積立に対応していない場合もありますので、毎月、自分で購入する事が面倒で、積立で運用して行きたい方は必ず事前に確認しておきましょう(自動積立ではなく毎月自分で購入する事も、投資しているという意識がありますのでおもしろいですけどね)。
★自動積立に対応している証券会社、銀行(2022年1月現在)
・SBI証券
・楽天証券
・マネックス証券
・野村ネット&コール
・ソニー銀行
上記は2022年1月現在の自動積立可能かどうかの状況です(上記の証券会社でも銘柄によっては積立ができないものもあります)。今後、積立可能な販売会社、銘柄は増えていくと思いますので事前に確認しておきましょう!
※投資を検討している投資信託の商品の過去のチャート、値動き、詳細情報は、「⇒Yahoo!ファイナンス」で確認することができます。
| 分散投資が面倒な方は・・・ | |
|
|
|
『国内株式・海外株式・国内債券・海外債券』、4つの市場、金融商品に分散投資することによってリスクをコントロールし、比較的安定したリターンを得る事ができるのは分かった。でも4つのインデックスファンドに投資すること自体面倒だ。という方もいるかもしれません。

そのような方にオススメなのが、『国内株式・海外株式・国内債券・海外債券』へのインデックス投信をセットにした商品です。
このようなセットにしたインデックス投信の数はまだまだ少なく、また4つの市場への配分は自分では決められず、信託報酬も若干、高めなのでそれほどオススメできないかもしれませんが、今後このようなインデックスファンドの種類も増加し、信託報酬も安くなれば十分、検討する価値はあるかもしれませんね。
ちなみに4つの市場+α(不動産投資REITなど)のインデックス投信をセットにした商品には以下のようなものがあります。
⇒eMAXIS Slim バランス8資産均等
| 関連記事 | |
|
|
|
⇒インデックス投信とは?
⇒インデックス投信で世界へ分散投資!
⇒インデックス投信の手数料
⇒インデックス投信の税金
⇒インデックス投信 vs 銀行預金(定期預金)
⇒インデックス投信 vs ETF
⇒インデックス投信の始め方
⇒ドルコスト平均法
 インデックス投信とETFで初めての投資信託♪では、リスクを避け、できるだけ確実に資産を殖やして行きたい方にオススメのインデックス投信(インデックスファンド)、ETF(株価指数連動型上場投資信託)についての説明、始め方、各ファンド、各証券会社の手数料の比較を具体的、かつ分かりやすく説明し、今日からすぐにでもインデックス投資信託を始められるように作成、運営しています。
インデックス投信とETFで初めての投資信託♪では、リスクを避け、できるだけ確実に資産を殖やして行きたい方にオススメのインデックス投信(インデックスファンド)、ETF(株価指数連動型上場投資信託)についての説明、始め方、各ファンド、各証券会社の手数料の比較を具体的、かつ分かりやすく説明し、今日からすぐにでもインデックス投資信託を始められるように作成、運営しています。
